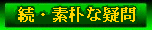 (13)
(13)
人はなぜあのようにザックを背負うのだろう?
最近、街中で小さなザック(*1)を背負った(*2)人をよく見かける。どうも世の中では、山登りをする人が急に増えたようである。
|
【注】(*1)昔はこれを“リュックサック”と称していたが、最近は単に“リュック”というそうである。何と呼ぼうが、結局はザック(sack)のことである。山男達は昔からこれをザックと称していた。リュックサックとかリュックなどとは決して言わなかった。ザックに付いている小物入れのことはポケットなどとは言わずタッシュと言ったものである。いずれもドイツ語である。
|
|
【注】(*2)ここは、“せおった”ではなく“しょった”と読んでほしい。“せおう”ではいかにも重く感ずる。しょうの方が軽いで“しょう”。以下同様。
|
私は、東京の西多摩地区を走る青梅線で毎日通勤しているが、ハイキングシーズンともなると奥多摩の山々へ向かうハイキング客で通勤電車が混むようになる。帰りは帰りで、疲れた身体で電車に乗り込むと奥多摩駅始発の電車は下山してきたばかりの登山客で一杯で、もう座る場所もない程の情況になっている。大抵の登山客は終点の立川まで行くから、こういうときはまず20〜30分は立ったままでいるのを覚悟せねばならない。昔、学生時代に登山に夢中になったことなどすっかり忘れて、私は「今日は日が悪かった」とただただ嘆息するばかりである。
ところが最近は、このような電車の中だけでなく街中を歩いている人たちまでが、皆申し合わせたようにザックを背負って(しょって、ですぞ)「今から山へ行きます」という格好をして歩いている。ただ、足元を見ると普通の靴やハイヒールを履いていたりして、とても山登りをするという風情ではない。
まあ、ザックを背負ったからといって、必ずしも山へ行かねばならぬという決まりもないが、私にはあのザックのパッキングの仕方がどうにも気に入らないのである。中の物(何かは知らぬ)がずっしりと下の方に沈みこんでザックの下後方が異様にふくらんでいる。後ろから何かに引っ張られているような感じで前かがみになって歩いている姿は、昔の買い出しのおばはん(古いなぁ)そっくりなのである。こういう人が電車の中で通路にでも立つと、ザックが邪魔になって一般乗客(ザックなど背負わず、山へも行かない善良なる人たち)は通れなくなってしまう。
学生時代、北アルプスや南アルプス連山を縦走したことのある者にとっては、このザックのパッキングの仕方がうまいかへたかで登山の実力の程が一目瞭然で分かるものなのだ。ザックの中身が均等に配置されていて、重心の位置が高くもなく低くもなく、できるだけ背中側に近いところに来るようにしなければならない。つまり、荷物が背中に張りついているように見えなければいけないのである。木こりや強力が使う“しょいこ”は、その意味では最も優れた担ぐための道具であると言われている。
だから、いい加減なパッキングの仕方のザックを背負って歩いている人を見掛けると、私は気になって気になって仕方がないのである。本当の山登りをする人は決してあのような背負い方はしないものだ。ザックを背負ったからといって山へ行かなくても構わない。しかしザックを背負うからには、もっとましな背負い方をしてほしいものである。
人はなぜあのようにだらしなくザックを背負うのだろう。あぁ、今夜も眠れそうにない。■
|



