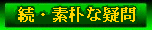 (18)
(18)
乗車運賃の表示はなぜいつも高い方に間違うのだろう?
鉄道各社の乗車運賃表示が間違ったまま長い間運用されていたことが判明した。こういうニュースが一度流れると、同じような事例があちらでもこちちらでもと次々に発見され新聞・テレビ等で派手に取り上げられている。最終的に運賃の誤表示は801駅、1852区間で発見され、運輸省はJR六社など全国の計二十二事業者に対し文書で厳重注意を行ったという。
取りすぎたた運賃は払い戻されるそうである。一部では数万円の払い戻しを受けた客もいるというが、客はどうやって自分の損を証明したのだろうか。参考のために是非知りたいものだ。もっとも、いろいろと調べてはみたが、悔しいことに(?)私が普段利用している路線の区間では何の間違いも起こってはいなかった。
人間のやることに間違いはつきものである。運賃表示がちょっと間違ったからといってそんなに大騒ぎすることもなかろうに、と私は思うのである(それは自分が損をしなかったからでもあるが)。ここは大目にみてあげるべきではなかろうか。
それにしても私にはどうにも解せないことがある。それは、これほど多くの間違いが発見されているのに、そのことごとくのケースで運賃表示が高い方に間違って設定されていた(らしい)という事実である。これはどう考えてもおかしい。同じ間違うなら、ほぼ同じ確率で安い方へ間違ってくれてもいいのではないか。
彼らが意識的に高い方へ間違えたとは思わないが、常に売上げ増を期待されているプレッシャーがそうさせたのかもしれない。ソフトウェア業界も彼らを見習い、システム開発でたとえ間違っても決して自分が損をしない方向に間違えるという高度な技術を身に付けられたらいいのになぁ、‥‥などと私は考えているのである。
それとも、実際は安い方へも間違っていたのだが、そういった事例はマスコミが取り上げる程の意義を認めなかったということであろうか(*)。もしそうならマスコミ報道も偏向していると言わねばなるまい。
乗車運賃の表示はなぜいつも高い方に間違うのだろう。あぁ、今夜も眠れそうにない。■
|
【注】(*)ここまで書いたところで、大江戸線では10〜50円分が過少表示されていたというニュースを見つけた(12月5日の朝刊記事から)。しかしその切符を買っても自動改札機ではねられてしまうのだそうである。やはり彼らは高度な技術を持っているに違いない。
|
 ある方から教えられた ある方から教えられた
電車の運賃計算は、目的地間の最短ルートに基づいて行われる。この最短ルートというのが曲者で、何回も乗り換えをした方が安くなることがある。普通ならそのような乗り換えなどするはずもないルートが最短距離になる場合がある。どのようなルートを選択しても、最短距離ないしはそれより長い距離になるから、したがって、安い方に誤って計算されることは絶対にない。 と言うのである。本当であろうか。
|



