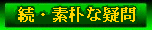 (23)
(23)
ウイルスパターンはどこまで大きくなるのだろう?
MSブラストと呼ばれるウイルスが猛威を振るっている。8月12日頃に発生したらしいが、13日の夕刊で報じられて以来瞬く間に世間の知るところとなった。16日以降に本格的な悪さをするよう設計されていたらしいが、19日の新聞の報ずるところによれば、それほどの被害はまだ出ていないという。本当だろうか。
特に、お盆休みあけの18日(月)あたりは極めて危険な日と見られていた。私めのコンピュータに対しても攻撃があるものと予想し注意深く観察していたのだが、はたせるかなかなりの数の不正アクセスの試み(Ping AttackあるいはEcho Requestとして記録される)(*1)らしきものが検出されている。
|
【注】(*1)“Ping Attack”があったからと言って即「不正アクセス」と決め付けることはできない。しかしPingは本来ネットワーク接続状況を確認するためのものなので、私めのコンピュータがネットワークに接続されているか確認するということは何らかのアクセスを試みようとした証拠と言える。
|
ファイアウォールのログを調べてみると、17日までは全く検出されていなかったPing Attack(あるいはEcho Request)の数が、18日になると異常に増えていることが分かる。拙宅のコンピュータ室にある常時接続(*2)のマシン上では1日に1239件にもなっていた。これは明らかに異常である。二階にある私の書斎のマシン(これは必要なときだけ立ち上げる)はトータルすると1時間40分程使ったことになっているが、その間にも528件が記録されていた。
|
【注】(*2)常時接続と言っても連続14時間程の使用であるが。
|
発信元のIPアドレスを見ると、ほとんど重複(*3)したものはなくそれぞれ異なるところから発信されているようである。思うに、MSブラストに侵入されたけれど、それを報告せずに自分で始末してしまった(あるいはまだ始末していない)マシンがかなりの数に上るのではないか(*4)。
【注】(*3)重複していたとしても、精々2〜3件に過ぎない。
【注】(*4)その後のニュースによれば、ウエルチという名前の新種ウイルスも関係しているらしいという。
|
ところで、私のマシン自体は幸いにしてウイルスチェック体制が整備されていたし、Windows Update を用いて早めにセキュリティホールをふさいでしまったので何の被害も受けずに済んでいる。
しかしこの間、ウイルスチェックプログラムのウイルスパターンは数回自動更新されているようである。つい数年前このウイルスチェックプログラムを導入したころは、使われていたウイルスパターンのサイズは確か2メガバイト前後であったと思うが、それが今や6メガバイト以上にふくれあがっている。この調子でサイズが増えていくと将来どうなるのであろうか。
今や、ウイルスチェックの環境なしでコンピュータを用いることは事実上不可能である。こういった数メガバイト規模のウイルスパターンをリアルタイム検出環境で常時用いなければならないとしたら、これが(どういうアルゴリズムでこのパターンを利用しているのかは知らないが‥‥)コンピュータの性能低下を引き起こしているのは明らかであろう。
その内にウイルスパターンの大きさに耐えかねて、ほとんどのマシンが動かなくなる事態になるのではなかろうか。
この点での唯一の心の慰めになるのは、ウイルスを作成してばら撒いているクラッカー自身も、多分この矛盾した環境にドップリとつかって居なければならないという点であろうか。
ウイルスパターンはどこまで大きくなるのだろう。あぁ、今夜も眠れそうにない。■
|



