◆肝臓に異常が?
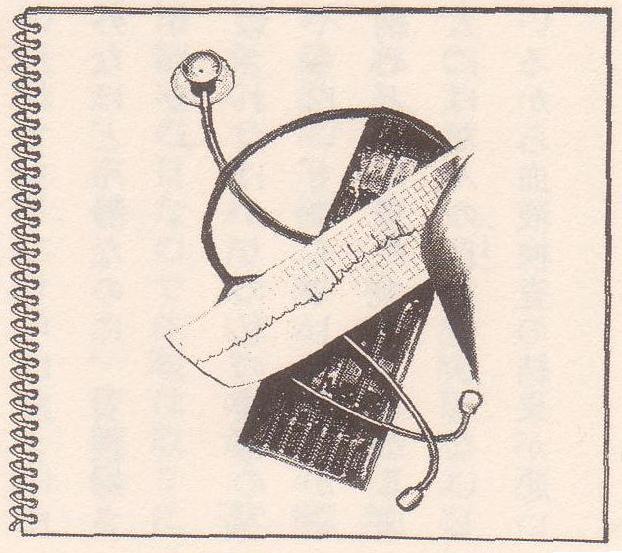 「カシャッ!」「カシャッ!」
「カシャッ!」「カシャッ!」
カメラのシャッターを押す音が何度もする。暗い検査室のベッドに横たわっている私の腹部に、検査技師が超音波診断装置の触手を当てながら盛んに写真を撮っている。
忙しい仕事に一応の区切りが付いたので、久し振りに健康診断を受けようと思い日帰りの人間ドックを予約した。9年ほど前のことであった。
以前受けたのは何時のことだったか、もうすっかり覚えていない。検査のやり方もずいぶんと変わってしまい、勝手が分からずまごまごしながらも何とか看護士さんの指示にしたがって手順通りに検査は進んでいった。ところが超音波診断装置による腹部エコーの検査では、やけに時間が掛かる。真っ暗な検査室の中でベッドに横たわっていると、女性の検査技師がバシバシと盛んに写真を撮っている。それも、同じところを何回も撮影しているようだ。顔を少し上げて装置の画面を覗こうとするのだが何も見えない。ちょっと不安になったが、特段何か言われることもなく次の検査へと進んでいった。
すべての検査が終り、外のレストランで昼食を済ませる。あとは医師との問診を済ませれば無罪放免となる予定だった。待合室でテレビなど眺めながら午後から始まる問診の順番を待っていると、まだ昼休み中だというのに看護士さんが慌てた様子でやってきて私の名を呼ぶではないか。検査の結果、肝臓部分に異常が見付かったのだという。急にそう言われても、こちらはあっけに取られるばかりで何と言っていいのか分からない。私の方は意外な程冷静なのに、看護士さんの方が慌てている。盛んに、気落ちしないようにと私を慰めてくれる。
自分の順番がきて医師との面談が始まった。医師は超音波で撮影されたばかりの私の腹部の写真を示しながら、肝臓部に影があるというのだ。なるほど、何やら白いもやもやした部分が認められる。それもかなり大きい。やれやれ、いよいよ私も年貢の納めどきが来たのか。しかし血液検査による肝機能の測定値には全く異常はないという。本人には何の自覚症状もないし、普段は酒も煙草もやらない。スポーツは努めてやるようにしているから血液検査の結果が悪い訳がないではないか。
◆精密検査を受ける
医師はできるだけ早く精密検査を受けた方がよいという。それでCTスキャン(1)とNMR(2)による検査を受けることになった。検査の日は5日後の12月28日であるという。検査の予定は年末までびっしりとつまっているが、医師の特別の計らいで最終日の最後に午後2時からCTの検査を、4時からNMRの検査をするようにあらかじめ予約を入れておいてくれたというのだ。否応を言っている場合ではなかった。この日は私の勤め先の方も御用納めの日なので休暇は取りにくいが、いたし方なかろう。
いよいよ検査の日となった。最初にCTの撮影である。人気のない検査病棟の廊下で一人ぽつねんと検査で呼ばれるのを待っていると、昔、医用機器技術研究所に勤務していたころの友人たちの顔が思い浮かぶ。当時同じ職場でCT、NMR(最近はMRIというらしいが当時はこう呼んでいた)、超音波などの研究開発をやっていた連中の顔がしきりと思い出されるのだ。彼等の作った機械で検査されることになろうとは、当時は全く予想もしなかったことである。
CTの検査が済むと、今度は別の検査室へ行ってNMRによる検査である。CTによる検査の方法は以前から知っていたので驚くこともなかったが、NMRによる検査は初めてで、その音の凄さに驚かされた。機関銃の発射音のような凄まじい断続音を発するのである。まるでガード下にいて道路にドリルで穴を開けているような具合であった。連中め、すごい代物を作ったものだ。
私が研究所に在籍していたのは、ちょうどNMRの製品開発がスタートしたばかりの頃であった。試験機で、れん根を輪切りにした写真を撮ってテストする段階から、製品化するための機械で人体の撮影をする段階へと検査対象が変わりつつある時期だったと記憶している<*1>。一方、CTや超音波の方はすでに素晴らしい実績をあげており、海外を含めた同業他社を圧倒していた。
|
【注】<*1>当時の学会論文には、れん根を輪切りにした写真がNMRの性能を示すためによく載っていたものだ。それを見た私は、NMRなど使わなくても包丁で輪切りにしさえすればれん根の穴の数なぞすぐ分かるのにと思ったりしたものである。
|
当時、同僚の中には、自分の頭を輪切りにした写真を自分の机の上に記念に飾っている者がいた。試験台になることを申し出れば、誰でも開発中の最新鋭のCTで脳の輪切り写真を撮ってもらえたのである。私は好奇心の強い方であったから、自分も自らの脳を輪切りにしたところを生きている内に一度は見ておきたいと思った。しかし写真を撮ってみたら脳の中が隙間だらけだったというのでは、同僚の手前何とも格好のつかないことになる。でも多分中身ががらんどうということはあるまい。そのくらいの自信は持っていたのである。
友人にそう言うと<*2>、彼はやめておけと言う。多分医者は喜んで撮影してくれるだろう。毎日れん根の輪切り写真ばかり撮っていたのでは退屈もしよう。本物の写真を撮りたくて彼等はうずうずしているのだ。しかし、良い写真を撮るために彼等は強力なX線を照射するのだという。何も好奇心のために無用にX線を浴びることもあるまいというのである。それもそうだ。それに自分の脳の輪切り写真を飾っておくなどという趣味はどんなものかと思い返し、私は友人の忠告にしたがうことにした。
|
【注】<*2>誤解のないように記しておくが、私が友人に言ったのは「(空でない)自信がある」ということではなく「輪切り写真を撮りたい」ということの方である。
|
そういったろくでもないことが懐かしく思い出される。しかし同時に自分が今置かれている立場を思うと、実に何とも情け無くなってくる。
NMRは、X線ではなく強力な磁気を用いて体内の原子核のスピンエネルギーの微妙な変化を捕らえて画像化するものである。したがってX線を浴びる場合のような危険はないと考えられていた。しかし強力な磁力が身体に及ぼす影響については、当時はまだ未知の分野であったという方が正確であろう(その後の研究でこの問題はどうなったのか、私は知らない)。
検査技師は撮影が終ったことを告げ、でき上がったばかりの写真を大型封筒に入れて私に手渡した。これを持って受付けへ行くようにという。技師は撮影結果については何も言わない。私も何も聞かない。
聞いてもそれに答えられる立場でないことを、こちらも十分に承知しているからである。しかし本当のところは、私には怖くて聞けなかったのである。彼の眼の中に何か同情の色でもあるかもしれないと覗きこんでみたが、何も読み取ることはできなかった。
検査が終ったのは午後5時をとっくに過ぎていたと思う。渡された写真を持って本館にある受付けへ行ってみると、既に待合室にはまったく人影がなく、ところどころライトも消されて実に寒々とした光景であった。受付けで写真を渡し指示を仰ぐと、先生はもうお帰りになったので次の診察日においでください。次の診察日は年が明けて1月9日ですという。これは何ということか、それまで結果はお預けである。私は受付けの前でただ呆然と立ちつくすのみであった。
そのときのことを今でもときどき思い出すが、どんな思いで帰宅したかはまったく覚えていない。ただ、あの無人の待合室の情景だけが脳裏に焼き付いているばかりである。
◆研究所時代のこと
悩んでいても仕方がないので、私は家に置いてあった家庭医学の本を紐解いて肝臓の病気について調べてみることにした。肝臓にも色々な病気があるものだ。肝硬変、ウイルス性肝炎(これではなさそうだ)、肝臓がん‥‥。ふむふむ。
肝臓がんは、早期に発見して可能ならば手術によって除去すべきであると書いてある。しかし、その発生した部位、肝硬変の合併によって手術の危険率が高くなる、などとも書いてある。やれやれ。読まない方がよかった。
一般に、機械には初期不良というものがある。しかし初期不良を無事に通過すれば、後は存外長持ちするものである。私の身体も機械と同じで、何の初期故障も起こさずに今まで順調に稼働してきたが、とうとう故障を起こす時期になってしまったものと見える。自分は特段運が強い方ではないから、多分初めての故障で一巻の終りとなるのではなかろうか。どうやら覚悟を決めておいた方がよさそうである。50代直前まで、よくもまあ連続運転を続けて順調に稼働してきた方ではないか。
それにしても、こういう状況になってみると医用機器の仕事を担当していた頃のことが無闇と思い出される。東芝が大型コンピュータの分野からの撤退を決め、我々はNTIS<*3>に出向してその後始末をしてきた訳であるが、その役割りを無事に終えて古巣の東芝に戻るとき、私は一人那須にある医用機器技術研究所勤務を命ぜられたのである。それまでコンピュータを開発する側であったのが、180度変わって利用者側になってしまったのだ。大型機の仕事ができないならコンピュータの仕事にはもう魅力は感じないと当時は思っていたから、自分なりにある程度の諦めをつけていた。しかし単身赴任しなければならないという事情も重なり、自分にとっては大変ショッキングな異動であった。
研究所では最初にX線CTの原理を学んだ。物体にX線を照射しそれを反対側で測定すると、物体を透過した線量が減衰する。これはX線が物体内の何等かの障害物に遮られるからである。しかしX線が通過した直線上のどの位置にその障害物があったかは分からない。物体を中心に回転することにより少し角度をずらし、再びX線を通して測定する。すると前の障害物の位置がある程度推定できる情報が得られそうに思えるが、今度は別の障害物が線上に現れてくるからやはり正確な位置は分からない。ところが物体の周りをぐるりと一周して全体を測定すれば、こうして得られた全データを付き合わせて処理すると(これをコンボリューションという)物体内部の障害物が上から見た形で(つまり輪切りにした形で)見えてくるというのである。私にはこの最後のところがどうしても合点がいかなかった。
職場の同僚たちは良い人達ばかりで、単身赴任で慣れない生活をしている私に何でも親切に教えてくれた。仕事の上でも、この論文を読むと分かりますよと言っていろいろな資料を提供してくれた。しかし私には、このコンボリューションの処理がどうしても実感として理解できないのであった。たとえ私がこの原理を完全に理解していなくても、別に何も困ることはないのだ。CTは売れているし毎日医師がCTを扱う上で支障となることは何もないのだから、どうでもよい話ではあった。しかし私の性格としては、曖昧な理解のままに先へ進むことがどうしてもできなかったのである。研究所は学位を持った人たちがごろごろ居るような職場だったが、彼等研究者達は泰然として日々の仕事に取り組んでいる。彼等は一体この仕組みを完全に理解しているのだろうか、曖昧な理解のままに妥協しているのではあるまいか、などと疑ってみたりしたものだ。いや、そんなことはあるまい。彼等は特別に頭の良い人達ばかりなのであろう。
そんなある日、全社的な委員会の場で久し振りにお会いしたY氏に「コンボリューションがよく分からなくて」とこぼしたところ、言下に「コンボリューションなど常識ではないか!」と言われてしまった。「それでもお前は数学科卒か」という顔をされてしまったのである。大いに恥じ入った私は、週末に家に帰ると早速学生時代のノートを引っ張り出して調べてみた。すると、これはしたり。コンボリューションというのは、重畳積分<*4>のことだったのである。重畳積分ならフーリエ変換のところで習ったことがある。しかし理論だけで、それが具体的にどういう意味なのか当時はさっぱり理解していなかったのだ。恥ずかしいことである。
【注】<*4>重畳積分の定義は、以下の通りである。
∝
f(x)=∫f1(x).f2(x-y)dy
−∝
|
学校を卒業して企業に入った当座は大抵の若者は血気盛んであり、大学で学んだ知識や技術が直ぐに業務で生かせると思いがちである。しかし大抵は1年もしないうちにこの予想がまったくの的はずれであったという厳しい現実を知ることになる。特にコンピュータの分野はその傾向が顕著で、次第に体力勝負を得意とするようになってしまったりする。しかしこの医療機器の分野では大学で学んだ理論そのものが、画像診断装置の理論的根幹をなしているのだ。稀有の分野というべきであろう。もっとも、医療機器開発の専門家から見れば異論はあるかもしれない。これらの製品は高度なハードウェア技術、ノイズ除去とか各種の画像処理技術などのソフトウェア技術の集積として製品化されているのであるから。しかし、少なくとも当時の私にはそう思えたのである。
私の単身赴任生活は2年間で終りとなり、結局古巣へ呼び戻されることになったのだが良い友人達に恵まれて貴重な体験をさせてもらえた研究所生活であった。私にとって何よりも参考になったのは研究開発の進め方である。それまでのコンピュータ開発業務では(少なくとも私は)理論もへったくれもなく、ただゴリゴリと腕力にまかせてやってきたように思う(それで存外通用していたのだ)。それはコンピュータ業界が新しい分野で、しっかりとした理論的な裏付けがまだ十分にできていない分野ばかりだったからである。しかし医療機器の分野を垣間見て、しっかりとした理論の上に立って堅実に研究を進めている第一級の研究者達に接することができたのは望外の幸せというべきであろう。
もちろん現在のコンピュータ業界にもしっかりとした理論的裏付けのある分野は増えてきてはいるが、それにしてもフーリエ変換とか重畳積分といったような重厚で奥の深い理論に匹敵するものは存在しないのではないかと思うがどうであろう。これは数学科出身の者のみが持つ偏見であろうか。何しろ数学というのは、紀元前の時代からの数千年の知識の積み上げなのだから、これと比較されたらどんな分野でも影が薄くなるであろうが。
◆滅せぬ者のあるべきか
さて本題に戻ろう。肝臓に致命的な欠陥があるらしいことが分かったのであるから、こんな風に昔を懐かしんでなどおれない状況である。しかし既に覚悟はできていたので不思議とうろたえることもなく、日々の暮らしを普段通りに続けていくことにした。ただ、与えられた時間が限られてきているという実感はあり、当時書きかけていた本の原稿を正月中に何とか仕上げてしまおうと必死になって頑張ったのを覚えている。そうすることによって、余計なことを考えないで済まそうとしたのである。
しかしこのように表向き平然としていられるのは、まだ正式の診断が下された訳ではないからであろう。不治の病と診断され余命いくばくもないと言われたら、これ程平静ではいられないかもしれない。いくら普段精神的に鍛えているつもりでも、いざというときになるとうろたえて自分を失ってしまうのはよくあることである。私の場合はどうなるであろう。私の両親は熱心なクリスチャンであったが、両親の死後私以外の兄妹はみなクリスチャンとしての洗礼を受けたのに、私のみは今もって洗礼を受けていない(そうかといって仏教徒でもない)。神の存在が信じられないとしても、いつか心の拠り所が必要になったときには洗礼を受けようかと思っている程度である。いよいよそのときが来たのかもしれない。
しかし後に読んだ「精神と物質」<*5>という本によれば、また考えも変わってくる。これは立花隆氏が、ノーベル賞受賞者の利根川進博士との対談を通じて最新の分子生物学の実態を詳述した本であるが、この本を読むと人間の存在は神の意思によるものではなく偶然の産物であることが明々白々と理解できる。神など存在しないという思いが確固としたものになってくる。宇宙科学などの最先端の科学に取り組んでいる欧米の科学者達(彼等は大抵クリスチャンである)は、この事実をどうとらえているのだろうか。神の存在について、自分の心の中でどう折り合いをつけているのだろうかと不思議に思うことがある。
しかしそう言っている私も、正月の初詣では深大寺<*6>へ行って神仏に家内安全と自分の身体の無事を祈ってきたのだから、やはり私も典型的な宗教的ノンポリの日本人なのであろう。調布市にある深大寺の開祖元三大師<*7>に祈願しながら、私の心の中には、もはやフィルム面に物理的に焼き付けられている診断結果がこうして祈ることによって変わるものではないという覚めた思いが浮かんできたのを正直に告白しなければならない。
【注】<*6> 東京都調布市深大寺元町にある天台宗の寺。
【注】<*7>正しくは慈慧(じえい)大師、または慈恵(じえ)大師という。正月の三日になくなられたので俗に元三(がんざん)大師と称する。
|
織田信長が好んだ謡に、次のようなものがあるという<*8>。
『人間五十年 下天のうちをくらぶれば 夢まぼろしの如くなり
ひとたび生を享け 滅せぬ者のあるべきか』
【注】<*8>「下天は夢か」津本 陽著:日本経済新聞社
|
仏の世界にも階級があり、その中の一番下の世界を下天という。人間の世界での五十年は、下天では夢まぼろしのようにまさに一瞬のことに過ぎない。どんなものでも必ず滅するときが来る。心悩ますことはなかろうという訳である。
信長はこれを謡いながら舞うのであるが、彼くらいの人でも『人間五十年‥‥』と心の中で唱えながら恐怖心に打ち勝つための拠り所としていたのであろう。
さて、このようにしてかくも長い長い正月休みが終り、いよいよ医者の診断結果を聞きにいく日となった。折しも昭和天皇崩御により平成という新しい年号に切り替わった翌日のことであった。
自分の順番がきて医者の前に座り宣告を待つ。医者は写真を取り出してじっくりと見ている。いやに長く感じられる。やおら、医者はこちらに向き直ると、こう言ったのである。「これは血管腫というもので、心配することはありませんよ」 ほ〜。
ほっとした私は、後の説明はうわの空で聞いていたので余り正確な記憶はないのだが、血管腫というのは要するに毛細血管のかたまりなのだという。顔にできる単なる「あざ」のようなものだと思えばよいのだそうである。私の場合は肝臓に先天的に毛細血管の塊ができていて、たとえば車の事故などで肝臓が圧迫されたりすれば大出血を起こして危ないことになる可能性はあるが、普通は放っておいても構わないものなのだそうである。最近は50人に1人の割合で発見されるという。超音波診断装置の性能が上がったために、以前は見えなかったものまで見えるようになってしまったのであろう。研究所の連中は罪作りなものを作ってくれたものだ<*9>。
|
【注】<*9>これらの製品で、彼等は1995年度の全国発明表彰総理大臣賞を受賞したのだから、確かに優れた解像度を持つものだったのであろう。
|
このようにして、我が人生最大の危機と(少なくとも本人は)深刻に思い悩んでいた事が、何とも恥ずかしいくらいにあっけない幕切れをむかえてしまったのである。
それにしても人間とは実に怠惰な生き物であることかとつくづくと思う。私は、再び以前の性格に戻ってしまったのだ。残された時間が少ないと、あれほど一つのことに全精力を投入していたことなどすっかりと忘れて、再び平穏で怠惰な日々を過ごすようになってしまった。しかしこれ以後、人間いかに死ぬべきかを真剣に考えるようになったのであるから、少しは成長したというべきであろう。そして、深大寺の開祖元三大師の効能あらたかであることを、身にしみて感じている昨今である(以来毎年の初詣では、必ず深大寺を訪れることにしている)。
◆システムの欠陥
さて、この話の教訓は、苦境に陥っても最後まで諦めるなというありきたりのことを言いたかったのではない。私の会社の医療機器の性能がいかに優れているかを言いたかったのでもない。ましてや健康診断に頼るより、神仏に祈った方が効果があると言いたかった訳でもない。私がここで自分の健康になぞらえて言及したかったのは、システムが先天的に持つ欠陥と、その欠陥への対応の仕方についてである。
コンピュータのソフトウェアには欠陥(虫)はつきものである。ちいさなプログラムなら完全に欠陥のないものを作ることは可能であろう。しかし大規模なソフトウェアになると欠陥を根絶させることはほとんど不可能に近い。我々が構築するシステムの複雑さなど、人間の身体組織を構成するシステムの複雑さには比ぶべくもないが、それでも開発要員が数百人/年の規模で数百万行のコードからなるソフトウェアなどになってくると、すべての機能を事前にチェックし尽くすことは絶対にできないし、容易には全体を管理できなくなってくる。これらのソフトウェアでトラブルが発生した場合、その原因の追及は極めて難しくなる。トラブルの再現さえもままならない。
ソフトウェアの事情にあまり精通していない人が、新たに着任してソフトウェア業務全般を見ることになったとしよう(世の中には、ままあることなのだ)。そういうとき、その管理者はソフトウェアの実態を知ってびっくりするのが常である。まずソフトウェアの欠陥のあまりの多さに驚く。更に、ソフトウェア開発者達がその欠陥の存在を当たり前のこととして容認しているらしいことを知り、益々驚くことになる。これにはさすがに我慢できなくなるのであろう、ソフトウェア開発というのは一体どうなっているのか! なぜ、最初から欠陥ゼロの製品を作ろうとしないのか、などとカミナリを落としたりする。
ソフトウェア技術者には元来素直な人が多いから(?)、このような発言を新鮮な驚きをもって聞く謙虚さを皆持ち合わせている。そう言われて彼等はひたすら恐懼し「なるほど、そうかもしれない」などと思ったりする。今までの自分たちのアプローチは間違っていたのかもしれない、と襟を正して真剣に反省してみたりもする(もっとも、最近はジーンズと丸首シャツで仕事をする若者が増えてきたから、正そうにも襟がない場合が多いけれど)。しかし結局は何も変わりはしない。暫く経つとまたもとの状態にもどってしまっているのが常である。残念ながら大型のソフトウェア製品では、欠陥を皆無にすることなどできないのが現状なのである。欠陥ゼロの製品を作ろうとする姿勢は大切であるが、それが達成できないからといって過度に悲観することはないのである。
ソフトウェアの欠陥というものは、疲労骨折のように使い過ぎたために壊れるという類いのものは存在しない。ソフトウェアのトラブルは元から先天的な欠陥として内部に抱えていたものが、あるとき何等かのトリガーが掛かりそれが切っ掛けとなって発生してくるのである。これはちょうど人間の持つ遺伝子にはどこかに欠陥があり、それが多くの病気の原因となっているのと同じことである。もちろんそういう欠陥を修復した際に、後天的に新たな欠陥が埋め込まれるということはあるであろう。しかし基本的には人間のDNA(3)に書き込まれている遺伝子情報に欠陥があるのと同じように、最初からシステム内に抱えていた欠陥が原因なのである。完全無欠な遺伝子を持った人間などいないであろう。だとすれば、最初から100%欠陥のないシステムを作ることが、いかに難しいことであるかが分かろうというものである。
こういった先天的な欠陥を完全になくして、完全無欠なシステムにしようとするのはむしろ無謀な行為といってもよいのではないか。欠陥の種類によってはそのままにしておいた方がよいものもある。たとえば、完全無欠さを目指すあまり、性能を犠牲にしてしまったのでは元も子もなくなってしまう。システムのセキュリテイーを完全無欠なものにするために、ファイルアクセスの性能低下を大目に見るなどはできぬ相談であろう。私も自分の肝臓の欠陥を外科手術で直し、完全無欠な身体にしようとは思わない。そんなことをすれば副作用を起こして寝たきりの身体になってしまうかもしれない。そうかといって肝臓を圧迫される危険に遭遇しないよう車の運転を控えたり、人込みの中に出ていくのを控えたりしようとも思わない。スポーツをするのを控えて家の中に閉じ籠った生活をするのなどはまっぴら御免である。
多少の欠陥はあろうとも、とにかくシステムを稼働させて実用になるようにうまく使いこなすことの方が重要である。厳然と存在する欠陥をどうやって早期に発見し、致命的な事故を未然に防ぐかという考え方の方がはるかに現実的なのではあるまいか。誤解を恐れずにあえて言えば、「欠陥がある程度残るのはやむを得ない。それを事前に見付けて致命的な事故をいかに防ぐかということの方が重要である」ということなのである。
この件があって以来、私は人間ドックを利用していない。その代わり毎年正月には深大寺に詣でることにしている。そして護摩をたいてもらって仏に祈り、住職のありがたいお説教をうかがってから、小説にも登場するあの有名な蕎麦屋で蕎麦を食するのを年中行事としている。現実を直視することを避け、こういった一連の“儀式”を済ませることで心の安らぎを得ているのである。
これは、欠陥があると知りつつ出荷したシステムが、何時か重大トラブルを引き起こすかもしれないと恐れながらも、ひたすらISO(4)基準に乗っとった出荷手順を守るという儀式を繰り返すことで心の安らぎを得ている最近のソフトウェア開発の実態とたいして変わらないと思うがどうであろうか。
【システムの信頼性】
◆新しいシステムを信頼してはならない。まだ機能が未完成で虫が取りきれていないかもしれないから。
使い慣れたシステムだからといって、これを信頼してはならない。いつなんどき不測のトラブルが起こるかもしれないから。
長く使い込んだ古いシステムなら絶対信頼してはならない。いつなんどきハードウェアトラブルが発生するかもしれないから。
【用語解説】
(1)CTスキャン
コンピュータ断層撮影
(2)NMR
磁気共鳴断層撮影(MRIともいう)
(3)DNA
細胞の核に含まれるデオキシリボ核酸のことで、遺伝子情報をもっている
(4)ISO
国際標準化機構 International Organization For Standardizationの略
|
(1995-11-13:掲示、1998-5-1:削除、2007-1-1:加筆修正・再掲示)