◆書道に取り組む
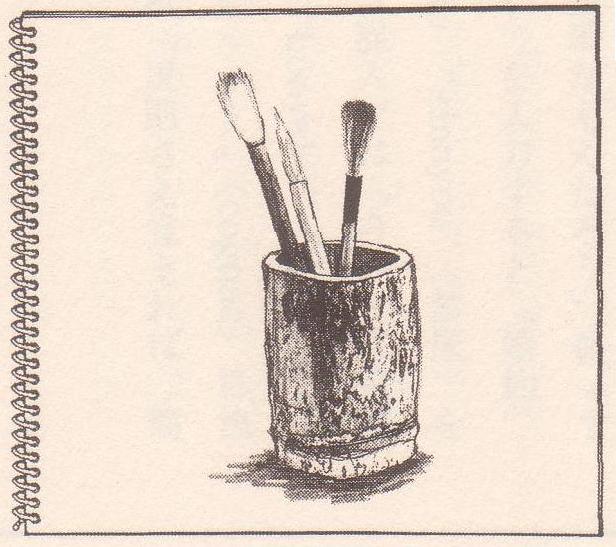 ワープロを使うようになって以来、とんと字を書かなくなってしまった。昔はよく正月になると「書き初め」というのをやらされたものだが、最近では筆で字を書くことなど滅多にない。世間では(一部の好事家を除いて)習字などにはまるで関心がなくなってしまったようである。それでいて年に一度の年賀状の宛先だけは毛筆体にしたいという。不思議な現象である。ワープロで毛筆体の出力が簡単にできるようになったためであろう。
ワープロを使うようになって以来、とんと字を書かなくなってしまった。昔はよく正月になると「書き初め」というのをやらされたものだが、最近では筆で字を書くことなど滅多にない。世間では(一部の好事家を除いて)習字などにはまるで関心がなくなってしまったようである。それでいて年に一度の年賀状の宛先だけは毛筆体にしたいという。不思議な現象である。ワープロで毛筆体の出力が簡単にできるようになったためであろう。
ところで、私は中学校に入るまでこの“習字”なるものをやったことがなかった。田舎の小学校だったからか、授業に書道を教える時間などなかったのである。実は田舎といっても東京の世田谷区にある小学校のことなのだが、当時(今からン十年程前)は世田谷は立派な田舎だった。この田舎の小学校を卒業すると、今度は渋谷という都会のど真ん中にあるS中学へと越境入学することになった。
この学校は当時“モデルスクール”と呼ばれ、開校したばかりのモダンな先進的教育を施す区立の中学校だった。生徒は地元の小学校から進学してきた洗練された都会の子供達ばかりで、そういう中で田舎育ちの私は一人コンプレックスのかたまりのようになって緊張の内に毎日の学校生活を送っていた。
私は大抵の授業では遅れをとるようなことはなかったが、習字の時間だけは別だった。何しろ私は、生まれてこのかた書道の筆というものを持ったことがなかった(見たことはあったが)。一方、悔しいことに、周りにいる学友達は小学校時代から書道を習っていたらしく皆習字の経験が豊富なのだ。中には書道塾に通っている者もいた。彼等は小学校時代からの友人ばかりでお互いに賑やかにやっているが、私の方は知った顔は皆無で最初の頃は口をきいてくれる友人もいないような状態だった。
その上、書道のO先生は取り分け厳しくて怖い先生だという噂だったので、気の弱い私は何時もビクビクしていたものだ。最初の授業での説明では習字だけでなくペン習字もやるとのこと(やれやれ、ペン習字なら何とかなるだろう)。
ところが、最初の授業では実際に筆を持つことはなかったからよかったが、2回目の授業のとき私は何を勘違いしたのかペン習字をやるものとばかり思い込んで書道の道具を一切持たずに登校してしまった。勝手に、習字とペン習字を交互にやるものと思い込んでいたのであろう。他の者は皆書道の道具を持ってきている。自分の勘違いに気付いたがもう間に合わない。筆を貸してくれる友人もいないので、私は仕方なく怖い先生の目に止まらぬよう、ひたすら小さくなって級友達が習字をするのを一人眺めていたものだ。実に惨めなスタートであった。
私が初めて筆で書いた字は“上”という字である。1画目の短い横棒を書き、次いで2画目の縦棒を書くべく筆を一気に上から下へと書き下ろしていくと、これは何としたことか、1画目の横棒とぶつからないではないか。だいぶ隙間ができてしまいそうだ。右側に少し筆の向きを変えようかという思いが一瞬心をよぎったが、そうもいかない。そのまま下へと進めるしかなかった。しかしその瞬間に分かったのだ。習字とは、細かい筆の運びよりも全体の構成であると。
書き始めた2画目の途中でこう悟ったのだから、我ながらたいした洞察力だと言うべきであろう。限られた紙幅の中に、いかに各々の文字とその文字の構成部分を配置したらよいかという全体のバランスの問題なのだ。それなら絵を描くのと同じことだ。私は絵を描くのは得意だったから、習字もとりあえずは絵を描く積りで取り組めばよいと覚悟をきめることにした(もっとも、楷書ならこの方針で何とかなるが、草書ではどうか)。
◆良い手本
当時、渋谷区では毎日新聞社の後援で書道展を毎年開催していた。各中学校から数名の代表が選ばれて、一堂に会した場で課題の字を書いてお互いに競い合うのである。1学期が終わる頃、書道のO先生は何を間違えたのか私にその書道展に出るようにという。これには正直のところ驚いたが、そうかと言って逃げる口実も見付からない。課題は「流れる白い雲」という6文字であった。先生が書いてくれた手本をもとに、夏休みの間に家で練習してこいというのだ。
そこは素直な少年であったし(断るまでもないが、今でも素直である)級友に対する劣等感もあったので、私は先生に言われるままに夏休み中何度か練習を繰り返した。この課題では、最初の“流”という字をいかにうまく書くかということと、漢字とひらがなの大きさのバランスが重要なポイントであると、私は賢くも看破したのである。そして、これならまあまあ級友に伍してやっていけそうだと思う程度にまではなった。後で知ったのだが、級友たちは誰も休み中に練習などしなかったらしい。こういった点が、要領の良い都会の子と田舎育ちの純朴な子との差だったのであろう。
夏休みが終わり秋を迎えると、いよいよ本番の書道大会である。練習でいくらうまく書けても、書道大会の会場でその実力が発揮できなければ何の意味もない。選抜された数人の仲間とともに見知らぬ中学校の会場まで出掛けていった。仲間といっても同級生は一人だけで後は上級生ばかり。顔を見知っている人はほとんどいなかった。彼等は普段書道塾に通っているうまい人達ばかりらしい。書道を始めて数か月というような初心者は私だけであったろう。
当時、渋谷区内の地理にはまったくの不案内だったので、私はその場所がどこだったのかまったく覚えていない。仲間とはぐれたらもう帰る道は分からないのだ。書道に自信がない上にそういう見知らぬ場所に連れてこられたという不安もあって、私は唯おどおどと彼等の後についていくばかりだった。そして最後列の席に座ってひとり小さくなっていた。最後列の席を選んだのは、もちろん仲間の姿を常に視野に入れておくためである。一人だけ置いてきぼりを食うことのないように抜かりなく座る場所を選んだのであった(そう、私にとっては習字どころではなかったのだ)。
各自に紙が4枚配られた。4枚書いてその中で自分が一番よいと思うものを提出するのである。私は2枚目を書いたところで自分なりに満足なものが書けたので後は書くのをやめてしまった。実は、一人置いてきぼりを食わぬよう、手早く終りにする必要があったのだ。前の方に座っている仲間達はまだ必死で書いている様子。やれやれ、これで迷子にならずに家へ帰れそうだと私は内心ほっとしたのであった。
後日、結果が発表されると、何と私の作品が特賞に選ばれていたのである。全くのフロックであろう。仲間たちはその場の雰囲気にのまれてしまって実力が発揮できなかったものとみえる。私はといえば、普段から緊張のしっ放しだったので、そのとき取り分け実力が発揮できないということにはならなかったのであろう。
2年目も同じ書道展に出場した。今度の課題は「明月照松風吹」の6文字である。ここで難しいのは、最初にある2つの“月”という字をいかにうまく書くかである。月の2画目の微妙な曲り具合をうまく表現できればほぼ成功であると、私はまたまた賢くも看破したのであった。
普段指導してくださる書道のO先生は、怖いけれど素晴らしく実力のある先生で、生徒が持っていた書道塾の教師の書いた手本などを見付けると「ここに力が足りないなあ」とか言って直してしまう程の人であった。今から考えると、私のような初心者でも書けるようになったのは、この先生に書いていただいた手本が良かったためであろうと思う。
書道展に出場する人は、放課後に特別に集められて事前の練習を何度もさせられたが、私にとっては手本の通りに真似て描けば‥‥いやいや、書けばよいのだから楽なものであった。先生は私が手本通りに書いたものを見て、満足そうに紙の左肩の辺りに朱で3重丸を付け「これを胸のポケットに入れて書けば大丈夫」と緊張しきっている私に向かって言ったものである。
私は根が素直な方であったから、先生の言うとおりにそれを折り畳んで胸のポケットに入れ大会に臨むと、またまた特賞をとってしまった。今度は自分の学校が大会の会場だったこともあり(迷子になる心配もなく)落ち着いたものであった。書道大会が終わってから校内で遊んでいると、一緒に出場した級友がやってきて私の作品が特賞だと教えてくれたのである。先生方が作品の評価をしている教室へ行って、窓からこっそりと覗いてしまったのだという。とんでもないことをするやつだ。生徒として、そういうことをしてもよいのか‥‥‥。
級友にさそわれた私は、友人の好意を無にするのも本意ではないので、仕方なく(?)覗きに行ってみた。しかしよく見えない内に廊下を通りかかった先生に注意され、結局覗くのをあきらめることにした。そうとも、模範的な生徒はそんなことはしないものだ。
半信半疑ではあったが、心の中で「やったぞ」と満足感にひたりながら帰宅したのを覚えている。これで、自分には少しは筋があるのかもしれないと思うようになった。
2年生の冬は大作に取り組んだ。明くる年の正月に明治神宮奉納書道展が開かれることになっていたからである。これは全国の小中学生を対象にした書道展で、特賞を取ると明治天皇が愛用された文鎮の模造品が貰えることになっていた。私はこの頃には書道に対し少しは自信がついてきていたので、頑張れば賞をとれるのではないかと高慢にも思うようになっていた。毎晩家で、それに応募するための作品を作るのに全精力を注いだものである。
今度の作品は今までのような小さな紙ではなく、長さ1.5メートル程の長い紙に書いて応募することになっていた。いつもとは少し勝手が違い、絵を描くような具合には手本通りに書けない。母親も書道についてはたしなみがあったので、でき具合については厳しく判定されたものである。「もう一枚書いてみなさい」と母親に何度も書き直しを命ぜられ、暖房のない寒い廊下に長い紙を敷いて繰り返し書いていたのを覚えている。しかし何という字を書いたかは忘れてしまった。
こうした努力の甲斐あってか、年末に入選を報せるハガキが届いた。賞が取れたかどうかは分からない。そこで三が日の間に明治神宮の回廊で開かれる展示会を見にいくことにした。しかし、いざ会場に行って並べられている自分の作品を見ると予想外に見映えのしない字なのでがっかりしてしまった。字に力強さが欠けているのだ。隣りに並べられた作品の方が数段うまく見える。栄えある特賞に選ばれたのは小学生の書いた作品で、「楽しい遊び」という5文字が太いどっしりとした筆使いで書かれていた。そのでき具合には文句のつけようがない程の素晴らしい作品であった。自分の作品は手本の通りに書けていたかもしれないが、力強さや個性というものが欠けていたのであろう。結局私の作品は佳作となり、明治神宮の絵が彫られた丸い文鎮を賞品としていただいた。
◆自分の字体
3年生のときも例年の書道展に出て三たび賞を取った(こういった他人の自慢話など聞いても読者は面白くも何ともなかろうが、話の展開上必要なのである。もう少し我慢をしてほしい)。現代風に言えば3連覇したことになるが、先生はそのことにまったく気が付かないようであった。私も当時はそれほど特別なこととは思わず、3連覇のことは誰にも言わなかった。もはや手本の通りに書けばよいという書道には、あまり関心がなくなっていたからでもある。それよりも高等学校へ進学するための受験勉強の方が最大の関心事になっていた。それ以後も何やかやと色々な書道大会への出場の話があったが、母親と相談した上ですべて辞退することにした。
書道のO先生のところへ行って、恐る恐る「受験勉強が大変なので、もう書道展には出たくないのですが」と言ったところ、以後はお呼びが掛からなくなった。しかし、これがいたく先生のご機嫌を損じたらしく、それ以後の書道の成績は5段階評価の3になってしまった。えげつないことをする先生だとは思ったがやむをえないことであろう。その代わり受験勉強の効あってか、希望の高等学校へと進学することができたのである。
高等学校では、特に深く考えることもなく美術の科目として書道を選択した。ところが運の悪いことに、その書道の先生は前衛書道の熱心な推進者だったのである。使う筆も特別製で、命毛をわざとなくした絵筆と同じような感じのものを使わされた。そして手本なしで自由奔放に書け(いや、描け)というのである。私のように手本通りに書くオーソドックスな字体は、前衛書道では最も嫌われるものだったのであろう。私の書いた字は散々にこきおろされたものである。それで多くの生徒が2年目にゴッソリとやめてしまった。私もすっかり嫌気がさして2年目からは絵画の方に転向してしまった。以来、自ら望んで筆を持つことはない。
筆を持つ機会があるのは、結婚式の披露宴などでの受付けで記帳するときくらいのものであろう(しかし最近ではマジックペンや筆ペンとかいう筆のまがいものしか置いてない場合が多い)。特に結婚式で仲人をしたときなどは特別な色紙に記名させられることがあるので、いい加減な字は書けない。こういうときだけは最大限気張って立派な字を書こうと努力する。そういうとき久し振りに筆を持つと、昔を思い出して筆にたっぷりと墨汁を含ませてグイと力強い字を書きたいと思うのだが、現実は厳しいものでなかなか思い通りにいかない。硯に墨汁が少ししかなかったり、先の方しか降ろしてない書きにくい筆だったりして、大抵は期待に反したお粗末な字しか書けない。普段筆を使い慣れていないから、いざという時に実力が発揮できないのだと思って諦めることにしているが、本当のところはどうであろうか。
よく「あの人は字がうまい」などという。そういう場合はどの字を対象にして言っているのだろう。私が普段書く字は実にいい加減なものだが、特別に精魂を込めて書けばかなり立派な字が書けるはずだと思っている(最近、その自信もいささかゆらいできているが)。けれど、そうやって特別気張って書いた字が自分本来の字だとは思っていない。やはり普段何気なく書いている字が自分本来の字体<*1>なのであろうと思う。きれいな字が書けるかどうかは、普段書いている字を対象にして判断されるべきである。そういう観点で見ると私の字体は決してうまいとは言えない。
|
【注】<*1>ここで“字体”と言っているのは個々の字の形だけを指しているのではなく、個々の字を書き並べて構成された文全体が表現しているその書き手に特有のあらゆる特徴・性質を指しているつもりである。特に、罫線のない白紙の上に書かれた文からは、どの程度その人が普段字を書き慣れているかなどを含めた色々な特徴が読み取れるものである。
|
このような自分固有の字体は、決して昔苦労した書道を通じて習い覚えたものではない。学生時代の勉学を通じて、あるいは普段の生活の中で長い時間を掛けて自然に身に付けてきたものではないかと思う。たとえば授業中に講義ノートを取るとき、きれいに書くことを第一義に考えていたら遅れをとってしまって実用にはならないであろう。きれいに書くことよりも速く正確に書くことが求められているのだ。その結果、後でノートを読み返して見て自分の書いた字が読めなくて苦労した経験は誰でも一再ならずあるはずだ。ある程度の速さで継続的に、しかも自然に書いた字が自分本来の字体なのである。私の場合、自分の字体が形作られたのは中学生の終りから高校生時代にかけてではないかと思う。子供の字体から大人の字体へと変ってきた時期でもある。
私の在学した高等学校は、ラジオの受験講座で講師として普段活躍していた有名な先生方が多数おられる学校だった。ありていに言えば大学受験の名門校である。そのせいもあり各先生方の講義はそれはそれは見事なもので、我々生徒がついつい聞き惚れてしまうような授業もあった。我々はそういう講義から色々な面で強い影響を受けたものだ。特に、先生が黒板に書く(板書する)字を生徒は自然に真似て書くことが多かったので、自分の字体を確立する上で一番強い影響を受けたのではないかと思う(もっとも、字がおそろしく下手な先生もいたが)。英語の授業では、先生の書く筆記体のつづりを見て格好良い書き方を見付けると、直ぐさま真似てみたりしたものだ。そういう細かい努力の積み上げから、自然に自分固有の字体が形作られてきたものと思う。
◆手書き文字の良さ
しかし最近のようにワープロが普及してくると、手書きで文字を書くことなど滅多にないような時代になってしまった。小中学生でも簡単にワープロを使いこなしているのを見ると、自分の手で字を書くという最も基本的な訓練をする機会が次第に失われつつあるのではないかと心配になる。自分の経験に照らしていえば、この時期は漢字を覚えるだけでなく字体を確立する上で最も重要な時期だと思うのである。彼等はこの時期にワープロと出くわすことによって、その貴重な機会を奪われようとしているように思えてならない。
その上、読むことはできてもその字を書けないという特異な才能を持った人材を多数育ててしまうという弊害も出てきている。今や、ワープロの日本語変換機能を利用すれば、辞書を引かずとも漢字のつづりを確かめたり送り仮名を確認したりできるようになってしまった。便利ではあるが失うものも大きいのではないか。たとえば、辞書を引く機会が少なくなったためか同音異義語の選択を誤るケースが増えてきている。また長い時間字を書き続けるという訓練もできていないから、たとえば情報処理技術者試験(1)の論文問題で、テーマにもとずいてあらかじめ用意した文章を書こうとしても、途中で手がガチガチになって書き続けることができなくなってしまったりするという。
ワープロの利用うんぬんの前に、もともと我々の周辺では字を書く機会が少なすぎるのである。最近の教育現場では、講義中に私語する学生が多いといって問題になっている。講義の方法に問題があるとか、授業についていけない落ちこぼれ学生の問題だとか様々な議論がなされている。しかし私に言わせれば、その原因は自分でノートを取らないことにあるのではないかと思う。先生の話を耳で聞き、それを自分なりに理解してまとめてノートに取る。この最も基本的な作業ができていないのだ。そうやって必死でノートを取っていたら、私語する暇などないはずではないか。
私はときどき、手書き文字の良さを見直す時期にきているのではないかと思うことがある。以前は、回覧書類などで会社幹部の手書きの文字に接することができたが、最近はそういう力強い迫力のある文書に出会ったことがない。こちらの提出した報告書の余白に、手書きのコメントをいただいたこともしばしばあった。そういうコメントには特に記入者のサインはなかったが、特徴のある字体からそれが誰の字か容易に判断できたものだ(こういう優れたパターン認識力は、決してコンピュータでは実現できないものであろう)。読みにくい字だが知性溢れる味わい深い字体のそのコメントに、どれだけ勇気付けられたことか、逆に落ち込んだりしたことか。
手書きの字体には、うまい下手は別にして書き手の人生経験、人柄などが滲み出てくるものである。最近はワープロ化された文書ばかりで、そういうものに接する機会がなくなって久しい。我々は週に一度でよいからワープロを使うのを止め、専ら手書きで文書を作る日を設けるべきではなかろうか。
以前私は“手書きワープロ”なるものの開発を社内で提案したことがあった。使い始めたときは普通のワープロだが、少しずつ自分の手書きの字体を登録していくと、何時か自分独自の字体による手書きの文字で文章が作れるというものである。自分が普段使う字だけを、一度だけ“精魂込めてきれいに書いて”登録すればよいのだ。そうすれば、後は「精魂込めてきれいに書いた文書」が何時でも自由に作成できるという訳である。登録されていない文字は活字体のままで表示されるから、自分が普段使わない字(あるいは、書けない字)を身不相応に使ってしまうというワープロ特有の問題も発生しない。
しかし、この提案はあっさりと却下されてしまった。世の中には自分の字に自信を持てない人の方が圧倒的に多いというのが現実なのであろう。自分の字に自信が持てなくても、年を経るにつれて人の書く字には味わいというものが出てくるものである。ワープロを売るという商売には、年を経るまで気長に待っていられない厳しさがあるのかもしれない。これからは字体と書き手の人柄とを結び付け、その書き手の持つイメージを思い出しながら読むということができなくなるのかと思うと寂しい。何とか、そういう高度(?)な読み方ができるようにする方法はないものであろうか。
◆プログラミングスタイル
プログラミングの世界でもプログラムの字体、すなわち“プログラミングスタイル”を確立することは常に重要な課題である。それにはプログラミングのプロが書いた良いプログラムを手本とし、それを読んで真似るのが一番の近道であろう。システムプログラムのソースリストを手に入れて解読しながら勉強するとか、市販のプログラミングの本に出てくるプログラムを利用するなど、手本<*2>はいたるところにある。
|
【注】<*2>ただし、市販の本に出てくるプログラムは出版用に特別に飾り立てた“よそ行き”のものであることが多く、普段のコーディング作業でそれを真似るのは難しい。したがって、場合によっては手本とするには相応しくないものもある。
|
初心者でも、最初から良い手本にもとずいてプログラミングを学べば、私の書道での経験を持ち出すまでもなく、かなりの短期間に良いプログラムが作れるようになる。初心者に手本なしでプログラムを作らせるのは、丁度前衛書道のやり方と同じで、多数の落伍者を出すのを避けることはできないであろう。
これは何も「初心者は何時も手本の通りに書け」といっている訳ではない。手本を真似るところから出発し、時間を掛けて次第に自分独自のスタイルを作っていけということである。習字にしたところで、何時までも先生の用意した手本の通りに書いていたのでは飽きも来るし、たいした進歩は望めない。そこから自分独自のものが出てこなければ、本当の意味で自分の字を書いたことにはならないと思うのだ。しかし自分独自のものをめざすあまり、いきなり手本なしでの前衛書道的アプローチでは初心者はついてこれないということである。
最近流行っているウィンドウズの環境下では、特別なプログラム作りの方法が取られることが多い。“ビジュアルプログラミング”とか称して、画面に表示された部品アイコンを適当に選んでいくとそれに対応するコード部分が組み込まれていき、自然にプログラムの骨格ができてしまうというものである。これで生産性は上がるのかもしれないが、こういう手法ばかり使っているとワープロの利用と同じで、個々人のプログラミングスタイルの確立は望めないのではないかと危惧している。
更に気になるのは、この手法では一般利用者が深入りしなくてもよいところはブラックボックス化してしまうという抽象化の技法が用いられているのだが、その“訳の分からないコード部分”がブラックボックスではなく直接目で見える形に残ってしまうという点である。つまり「お仕着せのコード部分」が自分のプログラムの大部分として居座るので、何時までもプログラムを自分で作ったと言う実感が湧かないのだ。深入りしなくてもよいプログラムの“はらわた”のような部分は、努めてソースプログラム上からは見えないようにすべきである。つまり“ビジュアル”にしないことの方が大切なのだ。オブジェクト指向言語でいう“継承”の機能やインクルードファイルの機能(2)は、まさにそのために用意されたものなのだからそれらを積極的に利用するのがよいであろう。
私が何時も疑問に思っているのは、この部品を選ぶという手法でプログラム作りを行う場合に、初めてのときは便利で良いかもしれないが、それ以後のプログラム作りでも(あるいはベテランプログラマになってからも)ずっと同じ方法で手本通りにやっていけ、ということなのであろうか。プログラムというのは、生き物のようにずっと生き続けるものである。使い捨てのプログラムもあるが、普通は何度も改造されたり再利用されたりして修正され続ける。その際この「お仕着せのコード部分」をどのように扱う積りなのであろう。そのままの形で、意味の分からないまま使い続けるのであろうか。それではいつまで経っても“自分独自のプログラム”を作ったと思えないのではないか。自分のプログラムでなければ、それを自分独自のコーディングスタイルに整えることなどできるものではない。
これは丁度、習字で“手本のままに書く”という段階にいつまでも止まっているのと同じことである。これでは、読む人を「なるほど」と感嘆させる美しいプログラムは作れない。あるいは「うむ」と唸らせるような味わい深いプログラムは生まれてこない。そういう個性的な良いプログラムを作れるようになりたければ、良いプログラムを単に真似るだけではなくそこから自分独自のものを作り出せるようにならなければならない。
それには、プログラム部品を自分でゼロから手書きで作ってみるという経験を、誰でも一度はしてみることであろう。■
【手本とすべき良いプログラムとは】
◆如何なる状況においても、上司の作ったプログラムは良いプログラムである。
【用語解説】
(1)情報処理技術者試験
国が行う情報処理技術者を育成するための各種試験制度
(2)インクルードファイルの機能
ファイルの中に他のファイルの名前を指定し、見掛け上そのファイルの内容が挿入されているように扱う機能
|