◆絵を描く
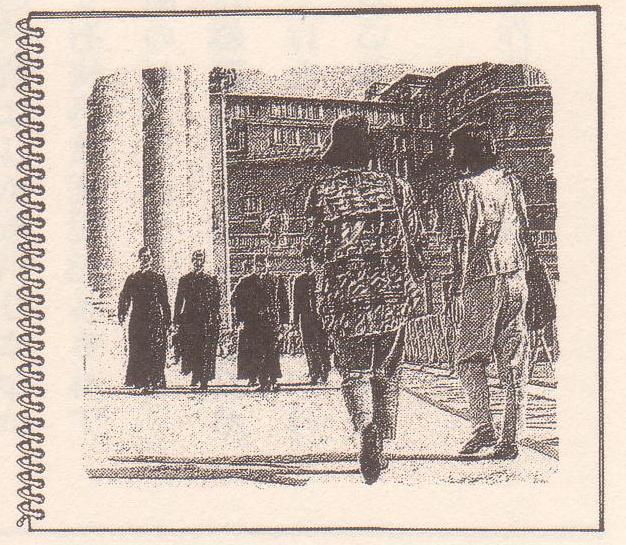 勤め先の会社が創立10周年を迎えることになった。記念誌を発行したり記念式典を催したりと、年間を通じていろいろな記念行事が企画され実行されてきている。その一環として、社員がお互いの美術作品などを持ち寄って10周年記念の“文化展”を開催したらどうかという話になった。
勤め先の会社が創立10周年を迎えることになった。記念誌を発行したり記念式典を催したりと、年間を通じていろいろな記念行事が企画され実行されてきている。その一環として、社員がお互いの美術作品などを持ち寄って10周年記念の“文化展”を開催したらどうかという話になった。
そこで、各職場から委員を選出し計画の立案と推進を行うことにした。我が部からはT君が委員として参加し、仕事の合間をぬって準備作業に追われている。できるだけ多くの人に作品を応募してもらいたいのだが、これがなかなかうまくいかない。出品を申し出てくれる人が少なくて苦労しているらしいのだ。普通は出来上がりに余程の自信がない限り、自分の作品を人に見せようなどという気は起こらないものであるから、これは無理からぬことであろう。
文化展開催を盛り上げて何とか成功させるためには、自ら率先して作品を応募し皆の関心を高める努力をする必要がありそうだ、などと私は殊勝な考えをおこしたのであった。しかし何で応募したらよいか。
応募規定を読むと、絵画、写真、生け花、など何でもよいと書いてある。絵など最近は全く描いたことがないから、写真で応募するしかなさそうだ。しかし写真での応募など、誰でも考えることだろうから面白味に欠ける。ここは、思い切って絵画で挑戦してみよう。この機会に何十年振りかで絵を描くのも悪くない試みだと思ったのである。
作品を応募する場合は、前もって作品のタイトルを書いて申し込んでおく規則なのだそうである。そこで私は、もし期待通りの絵が描けなかったときには、写真の応募で済ませられるよう絵画1点、写真2点で申し込み手続きを行うことにした。作品のタイトルは、抜かりなく「未定」と記入しておく。何も出展できなくなったときに“幻の作品”といって冷やかされないようにするためだ。そこはそれ、老いたりとはいえプログラマたる者の、万事に抜かりなく手を打っておく習性によるものである。
さて何を描くか。以前絵を描いたのは、たしか高等学校の時代に美術の授業でやったのを覚えているから、それ以来のことではあるまいか。その後、趣味で写生などを少しやった記憶があるが、何時のことだったか記憶が定かではない。そうだ、アメリカへ出張していたとき住んでいたアパートの部屋の中を写生したことがあった。しかし全くやっていないといってもよいくらいのものだ。
最近は仕事にかまけて絵を描きたいと思うことなど滅多にないが、定年後に時間ができたらやってみたいとはかねがね思っていた。安野光雅氏の絵が好きで、画集を買ってきてはときどき眺めたりしている。そして、こんな風に描けたらいいなあと思ったりする。ごてごてと色を塗らずに、さらっと仕上げた絵は水彩画の良いところが実によく出ていて、私には大変参考になる。
最近旅行したイタリアの風景でも描いてみるか。実はイタリア旅行中に、将来絵を描くことになったとき、それにふさわしい風景はないかと捜していたのである。もちろん、そのために写生をしに行くほどの余裕はないから、できるだけ景色を自分の脳裏に刻み付け、かつそれをカメラに収めてくることにしたのだ。旅行から帰って、旅行中に私が撮った写真を整理していた妻が「建物の写真ばかり撮って‥‥」とこぼしていたが、それはこの時のためだったのである。あれを利用することにしよう。
とりあえずヴェネチァの運河で見た風景を描くことにして、休みの日に少しずつ制作に取り組むことにした。自分の部屋にこもり写真を前に置いて鉛筆で下絵を描いていると、妻がときどき覗きにきて「プロはその場で描くもので、写真を見て描いたりはしない」などと悪態をつく。何を言うか「俺は、プロではない」のだ。
それに、私は決して写真を見て描いている訳ではない。脳裏に焼き付けられたイメージを思い出し、それを画用紙の上に再現しようとしているだけである。ただ、記憶の鮮明でない部分があれば、それは写真を利用して思い出し細部の補強にこれ努めているというのが実態なのである。
風景の現場で実物を見ながら描くのを一般に素描、走り描きなどという(デッサン、スケッチ、クロッキーなどともいう)。それに対し後で別の場所で描くのを“制作”というのである。私はその制作をしているのだ。
◆豪華な絵の具
鉛筆による下絵ができあがった。まずまずの出来であろう。これに安野光雅風にあっさりと色を着けただけで仕上げたい。絵筆や絵の具などの道具類一式は、次女が学校の授業で使ったものが残っていたので、それを借りることにする。
久し振りにパレットを開いて、その上で絵の具を溶いたり混ぜたりしていると、何とも言えぬ解放された優雅な気分に浸れるものだ。うん、これはなかなか楽しいものだ。時間さえ許せば、これからもずっと続けたいものである。
水彩画というのは、薄い色から塗っていくものである(自己流で、そうきめている)。自分の表現したい色をパレット上で作るのだが、どの色とどの色を混ぜれば自分の期待する色になるかは、これはもう勘に頼るしかない。多少期待する色と違っていても、後から別の色を上に重ねて塗ると下の色と混ざって微妙な色合いを出せるのが水彩画のいい点であろうと思う。娘の使い古した絵の具はチューブが空のものが多く、色合いを工夫する以前に必要な色の絵の具を見付け出すのに苦労する。しかし何とかなるだろう。あとはこちらの腕次第である。
などと考えながら色を塗っていると、‥‥どうもうまくいかない。期待した色は何とか出せるのだが、その上に別の色を重ねたときの具合がどうも変なのだ。だいぶ腕が落ちたと見える。こんなはずではなかった。段々と自信がなくなってきた。そういえばパレット上で作る色も、気のせいか何となく私が期待している色とは違うようだ。色を作る勘の方もだいぶ鈍ってきているようである。何しろ数十年振りに絵筆を持つのだから、これは致し方ないことであろう。絵画での文化展への応募はどうやら断念した方がよさそうである。
ところが、盛んに悲観している私を見ていた娘が「あら、これポスターカラーじゃないの」と言うではないか。何としたことか、私はポスターカラーで描いていたのだった。どうも感じが違うと思った。古い絵の具とポスターカラーとが、ごっちゃになって絵の具箱に入っていたので区別がつかなかったのだ。その中から適当な色を見付けては混ぜ合わせていたのだから、これでは水彩画のあの独特な色調は出せるはずがない。
見兼ねた長女が、翌日新しい絵の具を買ってきてくれた。私への誕生日の贈物にしてくれるというのだ。大いに感激した私はその絵の具を見て驚いた。30色もある本格的な絵の具なのだ。さぞかし高かったことであろう。昔は12色程度が普通で、それを互いに混ぜ合わせて好きな色を作っていたものだ。
後で知ったのだが、最近は12色、18色、24色、30色、さらには80色などという豪華なものもあるらしい。たとえば同じ“青”でも色々な種類の青が用意されている。各々のチューブには、固有の青を表すもっともらしい名前が付けられている。たとえば“プルシャンブルー”、“ウルトラマリンディープ”、“コバルトブルーヒュー”、“セルリアンブルー”、“コンポーズブルー”といった具合だ。要するに、苦労して色を混ぜ合わせなくても自分の期待する色に近いものがあらかじめ用意されているのだ。親切なことである。もはや好きな色を苦労して作る技術など必要なくなってきたのであろうか。
折角立派な絵の具を買ってもらったので、私はもう一度あのポスターカラーで失敗した作品を手直ししてみることにした。既に塗ってしまったポスターカラーの上に、更に重ねて色を塗ることになったので安野光雅風のあっさりした仕上げは到底期待できなくなったが、何とか作品の形に仕上げることには成功した。多少の不満は残るが、何十年振りかで描いた絵にしてはまずまずの出来上がりというべきであろう。題して「ヴェネチァの運河」とする。
◆過剰なサービス
娘が買ってくれたその豪華な絵の具箱を前にして、私は考えた。何か最近のソフトウェアの動向と似ているのではないかと思ったからだ。
最近のソフトウェアは肥大化しているという問題が、色々な場で指摘されるようになってきている。そして、同じような機能のシステムならもっとコンパクトに実現できると主張して、実際に作ってしまったりする学者も出てきている。しかし詳細に話を聞いてみると全く同じ機能ではなく、学者の立場からはこの限られた機能だけで十分なのだという主張が裏にあることが分かってきたりする。基本的な機能さえ用意されていれば、その組み合わせで大抵の要求には応えられるというのである。確かに、基本的な機能だけを巧みに設計すればコンパクトに実現できるのは事実であろう。そして、その機能差が全体のサイズの差となって表れてきているのも事実である。要するに最近のソフトウェアは過剰なサービスが多すぎるのだ。過剰サービスが肥満体ソフトウェア(次の章でふれる)の原因の一つなのである。
たとえば、最近のワープロの機能は重すぎるという声をよく耳にする。ミニ出版事業でも始めるなら必要となるであろう機能が、初心者向けのシステムに含まれていたりする。昔のテキストエディタは8KB程度だったのに、今はその100倍もの大きさになっている。処理速度も遅くなって、ハードウェアの高速化がなければとてものことでは使えないような代物もある。「必須の機能」と「あれば良い機能」との明確な区別ができていないのだ。利用者が欲しいと思う機能なら何でも構わず無差別に取り込んでしまおうとするから、どうしても過剰な機能を装備することになってしまう。
この過剰な機能競争は、雑誌などでの同種ソフトウェアの機能比較などの記事が影響しているのではないかと思う。利用者はその星取り表を見て、優れていることを示す○印の多い方を買おうとするからだ。開発者側もこの機能競争に負けないよう、争って新しい機能の導入に走る。その結果一般利用者なら滅多に使わないような機能、一部のプロフェッショナルしか必要としないような機能がどんどん標準仕様として取り入れられてしまう。
もっとも、ソフトウェア会社の立場からは一度リリースしたソフトウェアに対し定期的に機能を追加していかないとアップグレード版による収入は得られないのだから、当然の作戦というべきであろう。賢い利用者はこのアップグレード地獄に陥らないよう気を付けるべきである。
一般に肥大化したソフトウェアでは、ソフトウェアの構造が崩れやすくなるという。すべての機能が最初から単層構造で組み込まれてしまうからだ。システムに必須の機能をベースとし、その上に付加的に機能追加していけるような構造になっていれば、いくら機能追加してもプログラムの構造が崩れることはない。
同様に、利用者側も少し賢くなる必要があろう。基本的な機能をうまく組み合わせることによって、自分に必要な機能を実現する知恵を持つべきである。昔の絵の具のように、12色という限られた色だけでも、それをうまく組み合わせれば十分に自分の必要とする色が出せるものなのだ。もちろん、苦労して色を作らなくても最初からすべて揃っているようにしたい人は、そのようなシステム(80色の絵の具)を選択すればよい。しかし一般には12色で十分なのだ。それを、80色が普通であるかのように仕向けている最近の風潮が、何とも我慢がならないのである。
文化展への私の出品作は、結局絵が1点、写真が2点で最初に予定していた通りになった。最終的な応募作品の数は結構十分に集まったそうで、文化展の開催の方も成功裡に終了した。まずは、めでたい。
作品に対する評価は、見学者によるアンケート投票で決めることになっていたが、その評価結果によれば、私の絵「ヴェネチァの運河」は残念ながら1票差で最優秀賞を逃し優秀賞ということになった。写真も2点のうち1点が佳作となったのだから、私にとってはまずまずの成果というところである。
私の会社の若いソフトウェア技術者達は、美しいものを美しいと正しく評価する能力、いわゆる芸術に対する正しい鑑識力をちゃんと持っていたことになる。しかし、私が本当に自信を持って応募した作品は、佳作にも入らなかった写真「サンピエトロ寺院で出会った若い神父たち」というちょっと大袈裟で気取った題の付いた作品の方であった。それなのに「サンマルコ広場の夏」という、極めて絵葉書的な作品の方が入賞してしまった。写真に関しては、彼等の鑑識眼ももう一つというところなのであろう。
いやいや、絵が優秀賞に選ばれたからといって図に乗ってはいけない。入賞できたのは、若い技術者の年輩者に対する優しい思いやりだったのかもしれないのだから。■
【過剰装備のソフトが売れる理由(わけ)】
◆プログラマは、将来とも使う可能性のない機能でも、とりあえず何時でも使えるようにしておくことで心の安定を得る。
(1995-08-21:掲示、1998-5-1:削除、2006-5-1:再掲示)