◆イタリアの旅
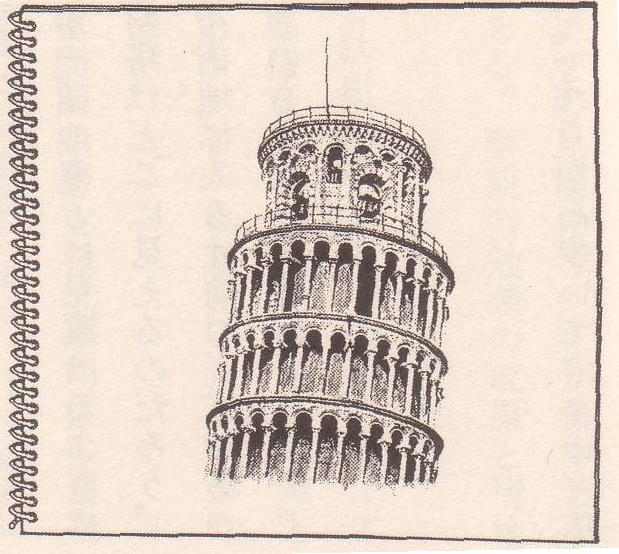 私は今イタリアにいる。フィレンツェから車で数時間のところにあるピサへと、バスで向かっているところである。バスは高速道路を出て,細い田舎道へと入っていく。道の両側には、崩れかけた赤煉瓦の壁の古い家々が並んでいる。崩れかけた壁の地膚というのは、絵を描くときの格好のテーマになるのだが、余りに車の位置に近過ぎてカメラのアングルに収めるのが難しい。折角のシャッターチャンスだというのに<*1>。
私は今イタリアにいる。フィレンツェから車で数時間のところにあるピサへと、バスで向かっているところである。バスは高速道路を出て,細い田舎道へと入っていく。道の両側には、崩れかけた赤煉瓦の壁の古い家々が並んでいる。崩れかけた壁の地膚というのは、絵を描くときの格好のテーマになるのだが、余りに車の位置に近過ぎてカメラのアングルに収めるのが難しい。折角のシャッターチャンスだというのに<*1>。
|
【注】<*1>絵と写真については「ソフトウェアと絵の具」を参照
|
バスの前の座席には、新婚旅行とおぼしき一組の夫婦が座っている。そして男性の方が8ミリビデオを使って、中央通路ごしにバスの先頭からの眺めを盛んに撮影している。私の位置からそのファインダー画面がよく見える。両側にポプラ並木の続いているひなびた道を、バスがゆっくりと進んでいく様が手にとるように見えるのである。最近のビデオカメラはファインダー画面もカラー液晶になっているらしい。しかし何もここまで来て、この美しい景色をファインダー越しに見ることもあるまいに。実物の方をしっかりと見ればよいのである。
もっとも、そう言っている私の方は、絵を描くときの適当な画題が見つかるとすぐさま写真を撮っているのだから、まあ五十歩百歩というところであろう。
バスが峠を越えると窓からの眺めは一変し、突然ピサの町並みが一望のもとに見渡せるようになった。バスはその市街へと向かって徐々に下っていく。ピサの斜塔はどこに見えるのだろう。なかなか見付からない。やっとそれと認めたのは、バスがピサの市街地に入る寸前のことであった。予想していたよりもずっと背の低い塔のようである。これがあの有名なピサの斜塔なのか。とうとうやって来たのだ。
◆ピサの美しさ
バスはドゥオモ広場の裏手にある駐車場に止められた。そこから歩いてドゥオモ広場へと向かう。ピサの旧市街の北にあるこのドゥオモ広場には、ピサの見所のすべてが集中している。ドゥオモの西側に洗礼堂、東側には斜塔、北側には墓地がある。事前の勉強の成果と現地で仕入れた知識とを、ここで若干披露することにしよう。
イタリアの観光名所の中でも、ピサは豪華・華麗という点では屈指のものであろう。12,3世紀の頃、地中海を制覇し東方まで勢力を伸ばしたピサの繁栄をそのまま物語るものだといわれている。これらの建物群はピサ・ロマネスク様式の代表であり、ピサに花開いた華やかな芸術の頂点を示しているものなのだそうである。なるほど、なるほど。
中心にあるドゥオモは、11世紀に建設が始められたもので、正面の4層をなす小円柱の連なりと巨大な3つの青銅の扉が見事な調和をなしている。早速、写真に収める(カシャ! これはカメラのシャッターをきる音の積り)。
内部には、チマブーエのデザインによるモザイクとジョヴァンニ・ピサーノ(ピサの芸術の中心人物)の説教壇とがある。天井から下がっているシャンデリアは、ガリレオ・ガリレイがその揺れるのを見て振り子の法則を発見する切っ掛けになったものとされている。これも写真に収める(カシャ!)。彼も退屈なお説教を聞きながら、あらぬことを考えていたのであろう。わかる、わかる。なかなか親しみの持てる人のようだ。
洗礼堂はロマネスク様式の土台の上にゴシック様式の天蓋が載った直径35mの巨大なもので(カシャ!)、その内部にはジョヴァンニの父ニコラ・ピサーノの説教壇がある(カシャ!)。天蓋がなかった頃は説教壇にある窪みに雨水を溜めて、それを洗礼に用いていたという。内部の音響効果は抜群で、すべての扉を閉めてから若い案内人がこの説教壇に片手を置いて見事な歌声を聞かせてくれた。その声の響きが朗々と洗礼堂の中に響き渡ると、響きがエコーして互いに相和し、何とも言えない厳かな雰囲気に浸れるのであった。実に素晴らしい体験であった。これは、後から天蓋を付けた結果できた偶然の産物であろう。
その後で、私は内部を見てまわっている最中に、ここで一声叫んでみたいという誘惑にかられ、どうにも自分を押さえることができなくなってしまった。そこで、恥ずかしげもなく一声「あ〜」と叫んでみた。すると、どうだ。これが、実に美しく響き渡るのである。ここで一人でカラオケをやったら最高であろう、などと私は一人不埒なことを考えていたのであった。
◆プロジェクトの難しさ
ドゥオモの東側にある斜塔は、本来“鐘楼”として建てられたものである(カシャ!)。以前は登ることができたそうだが、現在は倒壊の危険から守るために一般の立ち入りは禁止となっている。完成した1350年以来少しずつ傾き続け、現在は少なくとも垂直線から4.5mは傾いているという。ガリレオがこの塔を利用して加速度の実験をしたという伝説は有名であるが、その頃はどの位傾いていたのであろうか。
ここに到着した直後、バスを降りてドゥオモ広場に向かうとき、私はこの斜塔の真後ろの道を通ったのだが、真後ろから見たピサの斜塔は全く傾いていないように見えた。これは珍しい写真になると思って、私は早速カメラのシャッターを押した(カシャ!)。しかし、そのときファインダーごしに妙な物を見付けたのである。斜塔の真下に、鼠色のブロックが沢山積み上げてあるのだ。ガイド嬢の説明によると、それは鉛のブロックで、塔の倒壊を防ぐための重しにしているものだそうである。そうか、陰では保守にも大変な努力をしている訳だ。ここで私は「真っ直ぐなピサの斜塔と鉛ブロック」とでも題する珍作品をものにした。
今度は表に回って、一番傾斜角度が大きく見える位置から斜塔の写真を撮ることにしよう。説明によると、斜塔の先端に付いている避雷針が丁度垂直方向を示しているのだという。ドゥオモを背にしてカメラを斜塔の方角へ向ける(カシャ!)。このとき気が付いたのだが、ファインダーの中から見える塔の左端は垂直線から5度以上は右側に傾いているというのに、塔の右側の方は傾きが少ないように見える。塔の上部の方は、ほぼ完全に垂直になっている。つまり、倒壊しないように塔の先端部分だけが、グイと身を起こしたようになっているのだ(カシャ!)。これは明らかに塔の建設中に、既に傾き出していたことを示すものであろう。倒壊を食い止めるべく建設中に設計変更を繰り返し、技術者が悪戦苦闘した様がありありと分かるのである。塔の外周には螺旋状の回廊が作られているが(カシャ!)、その柱を見ていると、できるだけ左側に傾斜を戻そうとして柱の長さと間隔を調整していることが分かる(カシャ!)。なるほど、彼等は建設中から大変な苦労をしていたのだ。
基礎工事が不十分だったために建築中から傾きだし、結局傾きを防止できないで未だに保守に追われている。今や、建築費より保守費の方がべらぼうに高く付く結果になってしまっている。そうかといって、真っ直ぐな塔に建て替える訳にもいかない。
これは、我々の携わるソフトウェア稼業での経験にそっくりではないか。システム設計に失敗し、設計変更という応急手当てで何とかリリースはしたものの、ユーザートラブルへの対応で結局開発費よりも保守費の方が高く付く結果になってしまっている。そうかといって途中で止める訳にもいかない。これは大プロジェクトをなかなか中止できない日本人的発想と実によく似ているではないか。
ソフトウェア開発では、プロジェクトの進行にともなって最初の設計方針から段々とずれてくることがままあるものだ。顧客の要求の変化、予期せぬ事態の発生、最新の技術進歩の先取りなどの必要性からこれはある程度やむを得ないことであろう。ソフトウェア技術者はそれらの変化に対応すべく最大限の努力をし、かつプロジェクト倒壊の危機と戦いながら完成を目指している。ソフトウェアの開発作業というのは、大なり小なりこのピサの鐘楼建設と同じようなものではないか。つまり“ピサの斜塔”的な開発過程を経てきているものばかりだと言っても過言ではなかろう。
ピサの斜塔は倒壊してしまっては困るが、そうかといって補修して傾きがなくなってしまっても困る。観光の名所であり続けるためには、傾いたままで存在することに意義があるのだ。もはや本来の目的である鐘楼としての役目よりも、観光の名所としてのシンボル的な存在になってしまっている。それにともない、保守作業も益々難しくなってきている。
一方、我々の扱うソフトウェアは、プロジェクト倒壊の危機を乗り越えて無事完成に漕ぎ着けたとしても、その本来の役割・機能を果たすために存在し続けるものあってほしい。倒壊しそうになる程困難なプロジェクトだったという開発の経緯が評判になるだけでは、その存在意義はないと思うからである。
私はピサの斜塔に別れを告げる前に、もう一度カメラのシャッターを押した(カシャ!)。■
【プロジェクトの成否】
◆プロジェクトの成否は、予算の額とボスの忍耐力の強さで決まる。
(1996-09-02:掲示、1998-5-1:削除、2006-12-1:再掲示)