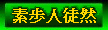 (5)
(5)
恐竜
── 環境への適応
会議が終り自席に戻ると、机上にメモが置いてある。大学の先生から電話があった旨の伝言であった。知り合いの某教授から電話があったらしい。12時半頃にまた掛け直すとも記されている。こちらから電話するのが礼儀ではあろうが、昼休み時だから先生は昼食に出ているかもしれない。そう思って私はそのまま自席で待つことにした。
電話は正確に12時半に再び掛かってきた。型通りの挨拶が済むと、先生は早速こう切り出したのである。
先生「最近、Windowsマシンを使うようになりましてね」
私「ほう、そうですか」
以前、先生はたしかUNIXマシンを使っておられたと記憶している。何でも、外資系の会社に勧められ価格の安さにつられて買ったはよいが、説明書などのマニュアルが日本語でないので往生しているということであった。そこで、東芝のUNIXマシンのマニュアルを贈呈して大変感謝されたことが思い出される。そうですか、先生もいよいよWindowsマシンを使うことになりましたか。Windowsは私の守備範囲だから何かと話が通じるかもしれぬ。
先生「しかしWindowsというのは、これがまた使いにくいシステムですなぁ。何ですか、あのfprintができないんですよ」
私「あぁ、‥‥まあ、そういうことですよね」
たしか1年程前に電話してこられたときも、同じようなことをおっしゃっていたのが思い出された。あの時は、たしか“fprint”ではなく「“printf”ができない」という表現であったと思う。C言語のプログラムで、テキストを出力するときの話である。プログラムの実行結果を直接プリンタ等の機器に出力する形態のプログラムが、Windows環境では素直に書けないというのである。あの時はたしか、一度ファイル上に出力しておいて後でまとめてプリンタに出す方法をとったらどうですか、とサゼッションしたのを覚えている。それで、fprintf関数を使ったのだろうか。それとも、単に“printf”を“fprint”と言い間違えたのであろうか。まぁ、どちらにしたところでたいした違いはないが‥‥。
私「Windows環境でのプログラミングは、確かに難しいですからね」
先生「そうなんですよ。学生に聞くと、『先生、この本を読めば分かりますよ』と本を渡されるんですが、それを読んでもよくわからなくてね〜」
私「はは〜。そうですか〜」
どうも、以前電話してこられたときからずっと、この問題で頭を悩ませているご様子である。先生はC言語のプログラミングの本を出版されたことがあるくらいだからC言語にはお詳しい方である。以前、ポインタ属性をどう学生に教えたらよいかで、相談の電話をいただいたことがあった。その時、ささやかながら私の意見を申し上げたことがあったのである。
先生「ちょっとした出力をするだけでも、大変な量のプログラムを書かなければならないんで、大変ですなぁ」
私「そうですね。しかし実は簡単なことなんですよ。本に書いてあるプログラムのスケルトン(骨組み)を利用して、そこに自分のやりたいことだけを埋め込んでいけばいいんです。スケルトンの意味なんかどうでもいいんですよ」
先生「はぁ〜。fprintで何とか出力する方法はないものでしょうか」
私「そうですね〜。Windows環境では、やはり一度ファイルに落としてから後でまとめて出力するしかないですねぇ」
先生「そうですか。無理ですか」
私「無理です。考え方を変えた方がいいですよ」
私は、以前の電話でなぜ難しいかを説明しなかったのを、今しきりと後悔し始めていた。先生は何とかその方法を見つけようと、ずっと努力されていたのであろう。なぜ、一度ファイルに落としてからではなく、直接出力しなければならないのか、そこのところが私にはも一つ分からない点なのだが、多分そういうプログラムを沢山お持ちなのであろう。それはそれとしても、ここらで一度、なぜ無理なのかを詳しく説明しておく必要がありそうである。
私「先生のWindowsマシンは、何人で使っているんですか」
先生「私一人ですよ」
私「あぁ、先生の専用マシンですか。プリンタは他の人と共用されているんですね」
先生「いや、私専用のものです」
私「あぁ、そうですか。すべて自分専用のなのに、以前のように自由には使えなくなってしまったという訳ですね」
先生「そうなんですよ」
先生は、やっと気持ちを理解してもらえたという様子である。
私「Windowsというのは、マルチプログラミング‥‥つまり多重プログラムが可能な環境ですから、特定のプログラムがプリンタ等の出力機器を独占してしまうような使い方は許していないんですよ。たとえば、Aというプログラムがプリンタを占有してしまうと、同時に動いているBというプログラムはプリンタが使えなくなってしまいます」
先生「はぁ、はぁ」
私「仮に、いくら先生が、私は二つのプログラムで同時にプリンタを使うような使い方はしていないと主張されても、一般にはそういう使い方ができるような仕組みになっているんです」
先生「ほう」
私「ですから、そういう環境に合うようにプログラムを作り変えるしかないんです。fprintという関数の使用はあきらめた方がいいですよ」
先生「はぁ〜、そうですか」
先生は甚だ不満そうである。
私「そういう環境の変化についていけないと、そうですね〜‥‥、まぁ〜‥‥、いわば恐竜のように絶滅するしか仕方のない運命になりますね」
先生「ははぁ〜。恐竜ですか。‥‥絶滅ですか」
私「そうですよ。環境の激変についていけない者は死滅します。絶滅するしかないんです(注)」
【注】後刻、妻にこの話をしたところ、妻は「絶滅するしかない」などと言うのは、先生に対して大変失礼な物言いであると眼をむいて怒るのであった。なに、先生はこの程度の喩えは理解してくださるし、ユーモアを解する方だから大丈夫であると私は主張したのだが、妻は到底納得しないのであった。実は、私もその絶滅しつつある恐竜の仲間の一人なのであるが(こちらの方は妻には言わなかったけれど)。
先生「はぁ、やっぱりそうですか」
私「そうですよ。だから、自分が恐竜のような絶滅の種になりたくなければ、この激しい環境の変化に対応していかなければいけないんです」
先生「そうですか。この歳になって大変な世の中になったものですなぁ」
私「ほんと、私もそう思いますよ」
先生「私もそろそろ定年でね。もっとゆっくりしたいんですがね〜」
私「後何年で定年なんですか」
先生「70才の定年まで、後2年もないんですよ」
私「ほう、でもその後も大学に残れる道はあるんでしょう」
先生「いやいや、もうゆっくりと休ませてほしいですよ」
私「はぁ〜。なるほど、そうでしょうね。‥‥ところで、今でもプログラミングの講座の方はやっておられるんですか。Fortranとかで‥‥」
先生「えぇ、まぁ何とか、ボチボチね」
私「私なんか、最近はもうCのプログラムを作るひまもありませんよ。表計算ソフトをいじっているばかりで。うらやましいことですね」
先生「いやいや、もうゆっくりと休みたいですよ」
Windowsの時代になって、それまで学部生に対する講義で使ってきたCやC++のプログラミング教材が、すっかり使えなくなってしまったのであろう。それを、Windows環境でも使えるようにするのは、これは結構大変な作業であろう、と私は先生にすっかり同情してしまったのであった。やはり、環境の激変についていけないと、どこの世界でも生き残れなくなる時代になってしまったのである。
先生「それじゃ、また」
私「はい。失礼します」
■


[ ] ]
|



