今だから話そう 出向と転勤で得たもの
 |
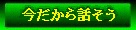 (9)
(9)
出向と転勤で得たもの
── 人間関係を大切に
 男ありけり 男ありけり
昔 男ありけり
関連会社に出向する身となりけり
コンピュータ技術者として最大の転機に直面せり
 出向 出向
1980年は私にとって忘れ難い年となった。
当時の私は、大型コンピュータのソフトウェア開発の仕事に取り組んでいたが、技術者として入社以来最大の曲がり角に来ていたと言えよう。
当時、日本では大型機に取り組む会社が6社もありどこも業績面で苦しんでいた。国の指導で2社ずつが組んで3つのグループに分けられたが、それでも状況はたいして変わらなかった。東芝(以下T社と略す)と日電(N社)とは同じグループに属し技術提携をしていた。T社が大型機を N社が中型機を担当していたが、ここで東芝は大型機の分野から撤退する決断を下したのである。大型機の分野はN社に移管されることになった。
移管するにはただ使用権を渡せば済むというものではない。それまでのT社の顧客が困らないようしっかりとしたサポート体制を作っておかねばならない。そのために必要な技術をN社へ移管する必要があった。
そこで、両社が共同出資の会社を作り技術者を出し合って一定の期間一緒に仕事をすることを通して技術移管を行うことになった。技術移管は1978年から始まっていたが、1979年からはいよいよ本格的な詰めの段階になっていた。
N社の本拠地である田町にある住友系のビルに、T社の大型コンピュータのソフトウェア部門を組織ごと移すことになった。そのビルには某航空会社の研修所があり社員食堂も一緒だったので、昼食時には同じテーブルにスチュワーデスの女性が座っていたりするような華やかな職場であった。
そのビルに移動した初日のことである。私が引っ越し荷物を整理していると、N社から来ているM取締役の秘書がやってきて私に「M取締がお呼びです」と言う。この忙しいときに何事かと行って見ると英文資料を渡されて「これをレビューしてほしい」と言うではないか。アメリカの学会誌に掲載されたM取締他数名の共著による論文のようである。既に掲載された論文を今更レビューしても仕方なかろうと思ったが、指示なので仕方なく受け取った。
その夜帰宅後、英文のチェックを行ない英単語の綴りのミスなどを見つけては赤鉛筆で徹底的に直してしまった。翌日その結果を持って取締の部屋へ行くと、英単語の綴りのミスの多さにあきれていたようであった。それを見て私は少し留飲を下げたが、特段の会話もないまま部屋を退出した。最初はT社の技術者を引き抜くのが目的かと心配したが杞憂であった。私の顔を覚えるのが目的だったようである。
出向先での私の役割は技術移転(ノウハウトランスファー)だったので、折衝相手のN社の技術者たちと頻繁に打ち合わせを行う必要があった。彼らは出向はしないでN社所属のままだったが我々のビルにやってくると、自由に我々の職場に入ってくることができた。逆に我々は彼らの職場には自由には入れないという環境になっていた。それでも、N社の技術講演会(*1)などの機会には、我々も参加することが許されていたのでN社のビルには出かけていった。【注】(*1)日電の技術講演会に出席したときの話は【ソフトウェア設計論】の「(7)【プログラミング】方言」で紹介されていますが、内容的に古いので参照は奨められません。書き直した版を「今だから話そう(10)部下の叱り方」に登録しましたので興味のある方は参照してください。
N社は、当然のことながらノウハウを持っているT社の技術者が欲しい。移管された資料だけではうまく使いこなせないかもしれないからである。したがって技術者の引き抜きも予想された。
一方T社側は、技術移管の仕事が終われば全員で東芝に戻ることを前提としていた。一般の社員は、所属する労働組合の合意がなければ勝手に他社に移籍されることはないから、本人がその気にならない限りN社側に引き抜かれることはない。しっかりとブロックされていたのである。しかし組合員ではない私のような管理者は、どこへ移動されるかは分からない立場であった。
私は仕事にケリが付けば全員一丸となってT社に戻るものと思っていた。そのことを忘れないよう私は日々部下たちに話し引き抜きにあわないよう徹底させていた。私自身も何故か一緒に出向前の(今は存在しない)職場に戻る積りになっていた。
 コンピュータ業務との別れ コンピュータ業務との別れ
しかし次の年の3月末に上司から私に対しての内示があった。
それによると、私が最初に東芝に復帰することになっていた。新しい職場は、医用機器の技術研究所であると告げられたのである。この内示を受けた直後、私はショックで言葉もなかった。顔からすっと血の気が引くのが感じられた。
内示段階だからこの事実は誰にも話せない。数日間一人で悩むことになった。T社の医療関係の工場や研究所は栃木県にあった。当然単身赴任になるであろう。これも予期せざることであった。
入社以来コンピュータ部門一筋できたので他の部門にはまるで関心がなかった。なぜコンピュータ部門ではなく医用機器なのか。後で聞いたところでは、医用機器の研究所の所長が名指しで希望しているという。そんなことが有る筈がない! 私は東芝側の撤収作業が始まったことを感じ取っていた。日電との間で何か論争があったのかもしれない。しかしそんなことは言っていられない立場になってしまったのである。
ソフトウェアの分野では転職はよくあることだった。主に大学に移るとか、外資系の会社に移る場合が多かった。いずれにしてもコンピュータ関係の仕事から離れる人はいなかったと思う。日本では競争相手の会社に直接移ることは道義的な慣例として許されていなかった。
私も転職することを一瞬は考えたが、会社の同僚たちに「全員一丸となって東芝に戻ろう」と言っていた立場だったことを思い出し、その言葉を自ら裏切ることはできないと思い返した。
たとえ仕事の内容が変わるとしても、仲間を裏切ることだけはしたくない。会社の友人や同僚たちとの人間関係を大切にしたいという思いの方が強かったのである。私は単身赴任の道を選ぶことにした。
1980年4月1日、私のみ東芝で正式示達を受けることになった。コンピュータ部門以外へ移籍する人はそうする慣例になっているらしい。そのため職場の仲間達への別れの挨拶もできぬまま慌ただしく離任することになった。
そして私は一人 医用機器技術研究所へ転勤となったのである。
 単身赴任の挨拶 単身赴任の挨拶
赴任する前に、私は大学の林先生に挨拶しておくことにした。
大学時代、先生に習ったコンピュータ関係の授業が契機となって、企業でのコンピュータ開発の仕事へと進むことになった。卒業後もいろいろとお世話になっている。コンピュータの仕事から医用機器の仕事に変ったことを、この際 報告しておく必要があると考えたのである。
報告がてら先生の研究室を訪ねると、激励されるかと思いきや最初の先生の一言が意外にも「大学に戻って来なさい」というものであった。そんなことは無理であることを私は重々承知していたが、その一言に救われたような気持ちになった。
新しい仕事がうまくいかなかったら戻ってこよう。そういう逃げ道を一つ与えられたような気がしてホッとしたのかもしれない。しかし一方で、そんな弱気なことでどうするか!と叱咤激励してくれる人がいなかったことが少し残念でもあった。
帰宅するまでの道すがら、私はいろいろと考えていた。あのような心に沁みる一言をさりげなく言えるのは凄いなぁと思う。やはり優れた教育者だからできることなのだろうとしみじみと思った。後々、その時のことを思い出しては、自分への励みとしているのである。
やはり、会社の同僚や友人達を裏切るようなことをしないで良かった。仕事が変っても、それまでの人間関係を大事にすることの重要性を再認識したのであった。


|
 |
|
| 


